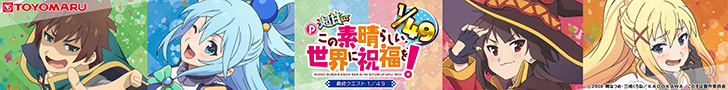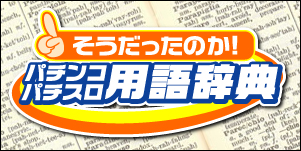「低貸低交換率」のホールに来店してみて亜流の可能性を感じた話
2025年10月10日(金)
先日、低貸低交換率のホールへ取材来店に行くことがありました。低貸営業はもはやどこの地域でも遊ぶことができますよね。パチンコに至っては1円パチンコ専門店も数多く存在しており、完全に市民権を得ているといっても良い。5円スロットもまた人気があります。しかしながら、景品への交換率は4円パチンコ20円スロットと同じにしていることが多く、そうなると1000円で遊べる玉数と枚数は多くなるものの、還元率は元来の4パチ20スロに比べて同様かそれ以下になります。このコラムを読まれている方々はそのロジックをすでに理解されていると思いますが、いま一度簡単に説明しておきましょう。
ホールは貸玉をすることによって売上を上げ、貸玉で遊んでもらった結果、最終的に景品に交換してもらい、その差額が利益になります。ただし4円パチンコと1円パチンコで比べると、同じ遊びに対して売上は4分の1となるため、還元率が同じ場合は利益も当然4分の1に。しかし1パチだからといって機械代が下がるといったことはなく(※低貸の場合は大半が中古機で経費削減されているが)、人件費や光熱費も同様です。つまり必要経費は変わらないので、少ない利益では店舗運営がままならないわけです。ということで、低貸営業は利益率をさらに高めで営業するのが常となります。例外はもちろんありますが、低貸営業は少ない投資金額で遊べるというメリットはあるものの、還元率は低いというのが事実。パチンコだと回転率にストレスを感じることも多く、パチスロでは高設定に出会えることは限りなく少ない。
さて、冒頭でお伝えしたように、“低貸”でさらに“低交換率”で営業しているホールにて取材来店を行いました。パチンコは1玉1円の貸玉料金、交換率は30年前を彷彿させる16割分岐です。当日はスロットを遊技したので、ここからはスロットオンリーの話になりますが、正確には1000円で125枚貸しとなり(つまり1枚8円スロット)、交換時には1枚5円となる計算です。1万円分=1250枚の貸しコインを投入して出た出ないを繰り返し1500枚ゲットしても、7500円分の特殊景品しか得ることができないレート。出枚数はプラスで終えても収支はマイナス……投資がかさむと取り返すのはかなり難しくなってきます。
4パチ20スロ、その地域のMAXレートで遊ぶことが当たり前の私。低貸もマイホで1円パチンコをたしなむ程度なので、普段と全く違う感覚で遊技できたのは面白かった。1000円125枚貸しなので、まず投資が抑えられる。これはもう基本中の基本で説明するまでもないこと。そして交換ギャップが生まれるゆえの戦略性。もちろん普段の勝負でも戦略性はあり、高設定を探したり、リセット後の挙動をどう考えるかなど、素人おじさんに毛が生えたような自分でもそれなりに考えて打っているつもり。そこに交換ギャップが絡んでくるとなると、初当りまでの投資をどうやって少なくできるかをはじめ、低交換率であるゆえに高設定を投入することもできるので、その高設定がどこに投入されているかを掘り当てるといった楽しみも同時に体感できます。
もちろん低貸低交換率のデメリットもあって、まず持玉遊技になってから粘れば粘るほど優位になるため、短時間勝負に向きません。もちろん「勝つ」ということを前提に考えたらにはなりますが、粘らないならオスイチを決めない限り勝てないです。また、全台が甘いわけではないので、ある程度は台の良し悪しを判別できないと、還元率は等価交換のホールに比べれば悪くなります。
低貸低交換率と聞くと、地元の年配層が遊びに来ているというイメージが強いと思います。私もそのように想像して当日ホールにお伺いしましたが、特にパチスロに至ってはかなり遊技機に詳しいユーザーが黙々と遊技している姿を見かけました。パチスロは知識介入の要素もかなりあるので、実力が結果に反映されやすい。もちろん大きくは勝てない=それだけで生活することは難しいゆえにプロっぽい人を見かけることはありませんでしたが、立ち回り方を「わかっている」ユーザーは多数見受けられました。これが一番びっくりしたことであり、亜流ではあるものの可能性を感じる営業方法だなと思ったのが個人的な感想です。現在主流の営業方法とゲームセンターの間の立ち位置とでもいえば良いでしょうか。連れ打ちなんぞには適した営業方法かと。こういったホールがもう少し増えても面白いかもしれませんね。
ホールは貸玉をすることによって売上を上げ、貸玉で遊んでもらった結果、最終的に景品に交換してもらい、その差額が利益になります。ただし4円パチンコと1円パチンコで比べると、同じ遊びに対して売上は4分の1となるため、還元率が同じ場合は利益も当然4分の1に。しかし1パチだからといって機械代が下がるといったことはなく(※低貸の場合は大半が中古機で経費削減されているが)、人件費や光熱費も同様です。つまり必要経費は変わらないので、少ない利益では店舗運営がままならないわけです。ということで、低貸営業は利益率をさらに高めで営業するのが常となります。例外はもちろんありますが、低貸営業は少ない投資金額で遊べるというメリットはあるものの、還元率は低いというのが事実。パチンコだと回転率にストレスを感じることも多く、パチスロでは高設定に出会えることは限りなく少ない。
さて、冒頭でお伝えしたように、“低貸”でさらに“低交換率”で営業しているホールにて取材来店を行いました。パチンコは1玉1円の貸玉料金、交換率は30年前を彷彿させる16割分岐です。当日はスロットを遊技したので、ここからはスロットオンリーの話になりますが、正確には1000円で125枚貸しとなり(つまり1枚8円スロット)、交換時には1枚5円となる計算です。1万円分=1250枚の貸しコインを投入して出た出ないを繰り返し1500枚ゲットしても、7500円分の特殊景品しか得ることができないレート。出枚数はプラスで終えても収支はマイナス……投資がかさむと取り返すのはかなり難しくなってきます。
4パチ20スロ、その地域のMAXレートで遊ぶことが当たり前の私。低貸もマイホで1円パチンコをたしなむ程度なので、普段と全く違う感覚で遊技できたのは面白かった。1000円125枚貸しなので、まず投資が抑えられる。これはもう基本中の基本で説明するまでもないこと。そして交換ギャップが生まれるゆえの戦略性。もちろん普段の勝負でも戦略性はあり、高設定を探したり、リセット後の挙動をどう考えるかなど、素人おじさんに毛が生えたような自分でもそれなりに考えて打っているつもり。そこに交換ギャップが絡んでくるとなると、初当りまでの投資をどうやって少なくできるかをはじめ、低交換率であるゆえに高設定を投入することもできるので、その高設定がどこに投入されているかを掘り当てるといった楽しみも同時に体感できます。
もちろん低貸低交換率のデメリットもあって、まず持玉遊技になってから粘れば粘るほど優位になるため、短時間勝負に向きません。もちろん「勝つ」ということを前提に考えたらにはなりますが、粘らないならオスイチを決めない限り勝てないです。また、全台が甘いわけではないので、ある程度は台の良し悪しを判別できないと、還元率は等価交換のホールに比べれば悪くなります。
低貸低交換率と聞くと、地元の年配層が遊びに来ているというイメージが強いと思います。私もそのように想像して当日ホールにお伺いしましたが、特にパチスロに至ってはかなり遊技機に詳しいユーザーが黙々と遊技している姿を見かけました。パチスロは知識介入の要素もかなりあるので、実力が結果に反映されやすい。もちろん大きくは勝てない=それだけで生活することは難しいゆえにプロっぽい人を見かけることはありませんでしたが、立ち回り方を「わかっている」ユーザーは多数見受けられました。これが一番びっくりしたことであり、亜流ではあるものの可能性を感じる営業方法だなと思ったのが個人的な感想です。現在主流の営業方法とゲームセンターの間の立ち位置とでもいえば良いでしょうか。連れ打ちなんぞには適した営業方法かと。こういったホールがもう少し増えても面白いかもしれませんね。